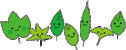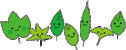平成22年度「全国学力・学習状況調査」の結果とこれからの指導に向けて
|
平成22年4月20日に実施された「全国学力・学習状況調査」の結果が8月末に文部科学省から提供されました。その結果を基に、本県の結果とこれからの指導についてお知らせします。
調査は、教科に関する調査(国語・算数)と質問紙調査(生徒質問紙と学校質問紙)で構成されています。また、教科に関する調査は、主として知識に関するA問題と、主として活用に関するB問題から構成されています。ここでは、主に教科に関する調査の結果について紹介します。
なお、今年度の結果については、県独自の採点による結果に基づいています。
|
| 平成22年度「全国学力・学習状況調査」の中学校国語(3年生)の調査結果について |
本県の中学3年生の平均正答率は平成19年度の調査開始からほぼ横ばいの状態で、A問題(主として「知識」に関する問題)よりも、B問題(主として「活用」に関する問題)に課題が見られる傾向は変わりません。改善の見られる項目も増えてはきましたが、設問ごとに見ていくと平均正答率の低いものや無答率の高いものもあり、更なる指導の工夫・改善が必要と考えられます。
佐賀県教育センターでは、知識・技能の定着をサポートする学習プリントや活用にかかわる学習プリントを定期的に作成し、提供していきます。ぜひご覧になり、ダウンロードして使っていただけたらと考えています。 |
| ○ A問題(主として「知識」に関する問題)での佐賀県の正答率 |
|
平成22年度 |
平成21年度 |
平成20年度 |
| 話すこと・聞くこと |
72.1 |
73.9 |
86.5 |
76.7 |
78.3 |
72.8 |
| 書くこと |
68.8 |
62.9 |
52.1 |
| 読むこと |
74.3 |
74.5 |
69.3 |
| 言語事項 |
75.5 |
76.4 |
75.2 |
|
| ○ B問題(主として「活用」に関する問題)での佐賀県の正答率 |
|
平成22年度 |
平成21年度 |
平成20年度 |
| 話すこと・聞くこと |
45.8 |
51.7 |
― |
74.5 |
― |
59.1 |
| 書くこと |
60.9 |
73.2 |
46.3 |
| 読むこと |
67.2 |
74.5 |
59.1 |
| 言語事項 |
― |
― |
61.6 |
|
| ○ 佐賀県全体の結果(設問別正答率及び無答率) |
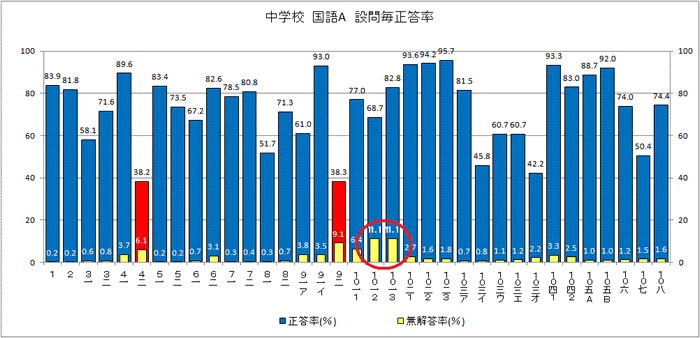 |
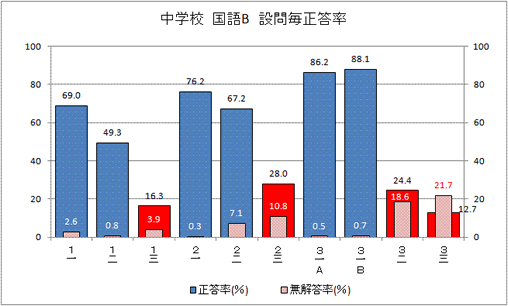 |
| 全国調査の佐賀県全体の設問別正答率で、特に正答率が低いものや無答率が高いものを赤色で示しています。この,課題であると考えられる赤色で示した設問について指導の工夫を提案します。 |
|
設問ごとの分析結果とこれからの指導に向けて [主として「知識」に関するA問題]
|
書
く
こ
と
|
設問番号
4二
正答率
38.2
無答率
6.2
|
〔設問の概要〕…一文を二文に分けて書く。
〔出題の趣旨〕…書いた文章を読み返し、読みやすく分かりやすい文章にする。 |
〈分析結果と課題〉
分かりやすい文章にするために、二文に分けたり、主語を補ったりすることに課題があります。述語に対して適切な主語はどんなものか意識して書くことができていないものと考えられます。主な誤答としては、二つの文に適切に分けて書くことができていない、内容が足りなかったり余計なことを足したりして意味を変えずに書くことができていない等があります。これらの誤答の要因としては、伝えたいことが何かを明確に把握していないことがあげられるでしょう。
《これからの指導に向けて》
推敲の指導においては、伝えたいことが明らかになるよう語句同士、文や段落相互の関係などについて確認させることが必要です。その際、文を修正する例を具体的に示し、推敲に必要な知識・技能を理解させた上で取り組ませることが効果的だと考えます。
|
設問番号
9二
正答率
38.3
無答率
9.3
|
〔設問の概要〕…小学生に向けた案内文となるように適切な文を書く。
〔出題の趣旨〕…相手に応じて表現を工夫して書く。 |
〈分析結果と課題〉
相手に応じて表現を工夫して書くことに課題があります。適切な言葉遣いができていなかったり、他の部分の記述に合った言葉遣いで書くことがきていなかったりして、小学生に向けた案内文となるように適切な文を書くという条件を満たしていないことが考えられます。このことから、相手や目的、場面などを意識して書くことができていないものと考えられます。公的な文章の様式に触れたり、相手や目的、場面などの条件に合わせて書いたりする経験の少なさがその要因と思われます。
《これからの指導に向けて》
案内文を書く際には、様々な相手を想定して、相手と自分との関係、伝えるべき内容などを踏まえ、それにふさわしい表現で書く経験をさせることが必要です。相手や場面を設定して、書きかえをする活動を取り入れた指導が効果的だと考えます。また、実用的な文章を書くための知識・技能を身に付けさせることが必要です。
|
読む
こ
と |
設問番号
8一
正答率
51.7
無答率
0.4
|
〔設問の概要〕…説明的な文章を読んで、「鳥とは違う」カモノハシの特徴を選択する。
〔出題の趣旨〕…論理の展開の仕方をとらえて、内容を理解する。 |
〈分析結果と課題〉
論理の展開の仕方をとらえて、内容を理解することに課題があります。「しかし」や「ところが」、「だから」という接続語に注意をしてはいるものの、論理の展開の仕方を完全にはとらえることができていないために誤答となっている生徒が、全体の四割程度います。
書かれている内容について整理して読むことができていないことがうかがえます。
《これからの指導に向けて》
読むことの指導においては、接続語や指示語などに注意して論理の展開を的確に把握させる必要があります。その際には、書かれている内容について箇条書きにしたり、図や表に整理したりしながら読むことが効果的だと考えます。また、文章の内容や論理の展開の仕方を的確に理解するために、形式段落ごとにばらばらにした文章をつなげてもとの文章に直す等の、書かれている事柄を再構成する学習も有効だと思われます。
|
| 言語事項 |
設問番号
10三イ
正答率
45.8
無答率
0.8
10三オ
正答率
42.2
無答率
2.2 |
〔設問の概要〕…イ−同訓異字から適切なものを選択する。(会議で決を採る)
オ−適切な語句を選択する。(兄は困っている人を見るとほおっておけない
性分だ。)
〔出題の趣旨〕…語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使う。 |
〈分析結果と課題〉
語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使うことに課題があります。同じような意味をもつ熟語を思い浮かべることができていないことがうかがえます。また、同じような意味の語句を文脈の中で適切に使い分けることもできていないものと考えられます。
《これからの指導に向けて》
語句の指導においては、語句そのものの意味を指導するだけでなく、多様な言語活動の中で実際に語句を使わせることで知識の定着を図らせることが大切です。そのためにも、ねらいの明確な言語活動を単元に位置付け、相手や目的、場面などの条件に合わせて知識・技能を活用する場として充実を図る必要があります。
|
設問番号
10七
正答率
50.4
無答率
1.5
|
〔設問の概要〕…行書の特徴の説明として適切なものを選択する。
〔出題の趣旨〕…漢字の楷書と行書との違いを理解する。 |
〈分析結果と課題〉
行書の特徴を楷書と比較しながら指摘することに課題があります。行書の特徴である、「点画の省略」、「点画の連続」、「筆順の変化」などの知識が身に付いていないために、書写における「省略」「連続」などの言葉の意味が理解できていないものと考えられます。
《これからの指導に向けて》
行書の基礎を指導する際には、同じ文字の楷書と行書とを比較し、「省略」、「連続」、「筆順の変化」などについて考えさせることが大切であり、これらを踏まえて行書で書くようにさせる必要があります。
|
|
設問ごとの分析結果とこれからの指導に向けて [主として「活用」に関するB問題] |
書
く
こ
と
|
設問番号
1三
正答率
16.3
無答率
3.6
|
〔設問の概要〕…新聞を読んで、興味をもった記事について感想を書く。
〔出題の趣旨〕…記事文に書かれている内容を基に、自分の考えを書く。 |
〈分析結果と課題〉
記事文に書かれている内容を把握し、それを基に自分の考えを書くことに課題があります。
主な誤答には、以下のようなことが見受けられます。
・
自分の考えが、「すごいと思う」や「よかった」といった感想にとどまっている
・ 書き手の意見を自分の意見のように書いたりして、自分の感想を具体的に書くことができていない。
・自分の感想は具体的に書くことができているが、記事文のどの部分に興味をもったのかが明確に分かるように書くことができていない
書かれている内容を正確に把握することができていないこと、引用部分と自分の考えを区別して書くことができていないことが、その要因として考えられます。
《これからの指導に向けて》
書かれている内容について自分の考えを書く際には、まず書かれている内容を正確に理解し、その上で、どの部分に興味や関心をもったのかなどを明確に示す必要があります。意見文等を書く際に、引用部分を明確にして自分の考えを書かせたり、文章を目的や意図に応じて要約したりする学習活動を通して、取り上げた事実や事柄と、自分の考えや意見などとを区別して書く経験をさせることが大切だと考えます。
※「授業実践一覧」の「意見文を書こう」「説得力のある意見文を書こう」をご参照ください。
|
設問番号
2三
正答率
28.0
無答率
10.3
|
〔設問の概要〕…資料の修正の方法を選択し、修正の具体的なやり方とその理由を書く。
〔出題の趣旨〕…資料の提示の仕方を工夫し、その方法について具体的に説明する。 |
〈分析結果と課題〉
提示する資料の修正の方法を選択し、具体的なやり方とその理由を書くことに課題があります。誤答の多くが、「題名を変える」「資料を提示する順番を変える」といった、修正の具体的なやり方については述べているのに、なぜそのように修正するのか、修正の理由を書くことができていないことから、問われていることを明確に読み取り、その条件に合わせて表現する力が身に付いていないと考えられます。
《これからの指導に向けて》
説明や発表などをする際には、自分の伝えたい内容がより効果的に伝わるよう話の構成や展開を工夫する必要がある。実際に「調べる→資料づくり→発表」を行う学習活動を設定し、その中で論理的な文章構成や相手を説得するための方法などについて考えさせることも有効です。また、作成した資料を見直して聞き手の立場に立って組み替えてみたり、実際の発表を相互評価したりする学習活動も効果的です。
|
読むこ
と |
設問番号
1二
正答率
49.3
無答率
0.8
|
〔設問の概要〕…トップ記事とコラム記事を比較し、書き方の特徴として適切なものを選択する。
〔出題の趣旨〕…記事文における表現の仕方をとらえる。 |
〈分析結果と課題〉
文章を読んで、その表現の仕方の特徴をとらえることに課題があります。文章の構成や展開、記述が果たしている役割などを的確にとらえることができなかったものと考えられます。文章を読む際に、その書き方の特徴に注目して読むことができていない現状がうかがえます。
《これからの指導に向けて》
読むことの指導においては、書き手が文章を書こうとした目的と、それに応じた表現の仕方に注意させる必要があります。そのためには、様々な文種に触れさせたり、それぞれの文種に応じた表現の違いについて考えさせたりすることが重要です。
※「授業実践一覧」の「構成と論理の展開に注意して読もう」「描写に注意して読もう」をご参照ください。
|
設問番号
3二
正答率
24.4
無答率
18.9 |
〔設問の概要〕…本文中の表現がたとえている内容をとらえて書く。
〔出題の趣旨〕…表現の仕方に注意して読み、内容について理解する。 |
〈分析結果と課題〉
比喩的な表現で書かれた内容について理解することに課題があります。たとえるものとたとえられるものとの関係を正確に理解できていないために、本文の一部を引用しただけでたとえる内容を明確に説明することができていない生徒が多くいます。
《これからの指導に向けて》
比喩的な表現で書かれた内容については、たとえるものとたとえられるものとの関係を的確にとらえることが大切です。たとえられているものがとらえにくい場合には、例えば、ペアやグループで語句から思い浮かべることができるものを出し合わせ、前後の文脈や文章全体の流れに沿って考えさせるなどの指導の工夫が考えられます。また、日常的に言葉を意識させたり、語彙を増やしたりする指導を継続的に行う必要があります。
|
設問番号
3三
正答率
12.7
無答率
22.1 |
〔設問の概要〕…二つの表現に共通した面白さについて自分の考えを書く。
〔出題の趣旨〕…文章の内容や表現の仕方をとらえ、自分の考えを明確に説明する。 |
〈分析結果と課題〉
特徴的な表現に共通した面白さについて自分の考えを書くことに課題があります。主な誤答には、どちらか一方の特徴的な表現にだけ注目して、両方に共通した面白さとして説明できていないもの、本文の一部を引用しただけで、その表現がどのように面白いのかを説明することができていないものがあげられます。求められた形に合わせて、自分の考えを明確に表現するための語彙力と技能が身に付いていないものと思われます。
《これからの指導に向けて》
読むことの指導においては、書かれている内容についてだけでなく表現の仕方についても考えさせる必要があります。そのためには、文章における特徴的な表現を取り上げ、その働きや役割などを考えさせることが大切です。授業の中で、表現の違いや表現の面白さを認識させるよう心掛ける必要があるでしょう。また、対話や話合い活動、考えたことを文章化する活動などを日常的に取り入れることも有効だと考えます。
※「授業実践一覧」の「描写に注意して読もう」をご参照ください。
|
|
| 〈参考〉国立教育政策研究所Webページ http://www.nier.go.jp/index.html |
|
以上のように分析及び考察を行いました。
詳しい結果や指導のアイディアなどを知りたい方は下記のリンクを参照してください。 |
○調査結果の詳細は 〜佐賀県教育委員会Webページ
http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1018/ik-genba/_48207/_48219.html
○平成22年度全国学力・学習状況調査結果を踏まえた実践アイディア集
〜国立教育政策研究所Webページ
http://www.nier.go.jp/10chousakekkahoukoku/22_chuu_jugyou_idea_houkoku.pdf |
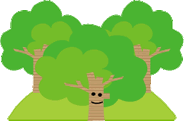 |