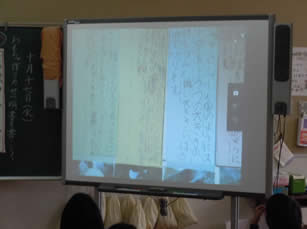| 〈本時の実践例〉 6・7/9 | |
| (1) 目標 |
○
| (2) 指導の実際 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 前時の学習を振り返り、本時のめあてを確認する。
|
○ 教師作成の「なるほどせつめいカード」を提示し、説明の工夫を見付けさせる。 ■ 「しかけカードの作り方」の学習で学んだ表現が分かるスライドを電子黒板で提示する。 |
|||||||||||||||||||||||||
2 「作り方」を書く。
 |
○
〈はじめ〉の部分は、何の作り方を説明するのかを一斉指導で書かせる。 ○ 〈中〉の部分は、4つの段落で、色分けした短冊に書かせる。 ○ 4枚の挿絵に合う文章を考えさせる。 ○ 以下の言葉を使って書いている児童を称賛する。
|
|||||||||||||||||||||||||
3
出来上がった短冊を読み返す。 【予想される児童の発言】
|
○ 短冊と短冊の内容がつながっているか、短冊と挿絵が合っているかを確認させる。 ○ 説明の工夫を入れて書くことが出来ているか、グループで検討したり、違うグループの児童にアドバイスをもらったりするように促す。 ○ 必要に応じて、挿絵の差し替えや文章の修正をさせる。 ■ 出来上がった児童の短冊を電子黒板で掲示し、作品の全体としてのつながりやまとまりに視点を向けさせる。
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 チェックカードに振り返りをする。 | ○ チェックカードに、書き終えた作品の自己評価をさせる。 ○ 短冊を「なるほどせつめいカード」に貼らせる。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 5 次時の学習について見通しをもつ。 | ○ 出来上がった作品を読み合って交流することを知らせる。 |